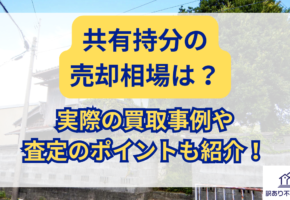
共有持分の売却相場は?実際の買取事例や査定のポイントも紹介!
詳しく見る
「共有者の持分が差押えられたけど自分には影響あるだろうか」そのような疑問を持っている方もいるでしょう。
共有不動産で共有者が差押えにあうと、少なからず自分にも影響が出ます。
対処によってはリスクを避けられますが、差押え状況や住み続けるか手放すかの意向によっても適切な方法は異なるので、正しい対処方法を理解しておくことが重要です。
この記事では、共有名義の不動産の差押えやそのリスク・対処方法について分かりやすく解説します。
目次
共有名義の不動産とは、所有者が複数人いる状態の不動産です。
たとえば、夫婦で住宅ローンを組んだ・複数人の相続人で相続したといったケースで共有名義になります。
共有名義の不動産は、自分以外にも所有者がいるため予期せぬ差押えに遭うケースがあります。
ここでは、そもそも差押えが何なのかやその主な原因をみていきましょう。
差押えとは、国によって私物財産の処分を禁じられる強制執行の手続きです。
債権者のお金の回収を目的としており、差押えされると所有者でも勝手に売却や処分はできません。
差押え対象となるのは、主に現預金や有価証券などの動産・不動産および給与や売掛金などの債権です。
また、共有名義の不動産であっても、現金化が可能な資産であるため対象です。
不動産が差し押さえられても、その時点では住み続けることができます。
しかし、競売によって新たな所有者が決まると、所有権を失い、退去しなければなりません。
なお、差押えは裁判所または行政機関のみが行えます。
そのため、債権者が差押えを希望するときは、裁判所に申し立て認められる必要があります。
差押えは、未払い金の回収を目的として行われます。
何が未払になるかという違いはありますが、代表的な原因は以下の3つです。
住宅ローンを組む際には、基本的にその家を担保として抵当権が設定されます。
抵当権とは、契約者(債務者)が住宅ローンの返済ができなくなった場合に、金融機関が(債権者)がその家を売却し、債権を回収できる権利です。
そのため、契約者が住宅ローンを滞納すると、金融機関は抵当権に基づいてその家を差し押さえることができるのです。
ちなみに、抵当権の設定がないと差押えするには訴訟などの手続きが必要ですが、抵当権があれば訴訟なしで差押えを申し立てられます。
各種税金を滞納すると行政から差押えを受ける可能性があります。
行政による差押えは法的手続きに基づいて行われるため、裁判手続きは不要です。
裁判所が差し押えた不動産は「競売」で、行政機関が差し押さえた不動産は「公売」で売却されるという違いもあります。
不動産を担保としない債権や借金の未払・延滞でも、債権者は裁判所で手続きすれば差押えが可能です。
ただし、その場合、債権者は差押えにあたり債務名義の取得が必要になります。
債務名義とは、債務者に借金を支払う義務があることを証明する公的な書類で、裁判所や公証役場の手続きにより取得可能です。
つまり、不動産を担保にしていない借金でも、債権者が裁判所で手続きをして債務名義を取得すれば、差押えが実行される可能性があります。
上記により他の共有者の持分が差し押さえられた場合、自身にも影響が及ぶ可能性があるので、注意しましょう。
共有名義の不動産の場合、債務者の持分のみが差し押さえの対象となります。
自分が債務者・連帯保証人でない以上、自分の持分が差し押さえられることはありません。
しかし、共有者の持分は差し押さえられるため、自分にも少なからず影響は出ます。
ここでは、差押えが共有名義の不動産に与える影響についてみていきましょう。
差押えられるのは滞納者の持分のみとなるので、滞納者以外の共有者の持分に影響はありません。
たとえば、滞納者の持分が50%、自分の持分が50%であれば、差押え後であっても自分の持分50%は守られます。
ただし、滞納しているのが固定資産税の場合は、共有者全員が納税義務を負うため、不動産を丸ごと差押えられる可能性があるので注意しましょう。
滞納者の持分が差押えられた後、競売で第三者が買い受けると、買主が新たな持分の所有者となります。
見ず知らずの第三者が共有者に加わることで、以下のようなリスクがあるので注意しましょう。
共有不動産を丸ごと売却するには共有者全員の合意が必要です。
誰か1人でも反対する人がいると売却できないため、新たな共有者と合意形成ができずに売却できない可能性が出てきます。
また、共有者は建物を利用する権利を有するので、買受後に敷地や建物に入ってくる恐れがあります。
しかし、共有者である以上、不法侵入ではないので追い出すことはできません。
新たな共有者が建物に居住しない場合、その共有者は、実際に住んでいる他の共有者に対して、自身の持分割合に応じた賃料を請求する権利を持ちます。
共有者が不動産を活用せず、自分だけが居住している状態になると、予期せぬ「持分の使用量(賃料)」を請求される恐れもあるので注意しましょう。
共有状態の不動産は制限が多いことから、新たな所有者が他の共有者の持分買取を迫ってくるケースもあります。
とくに、悪質な業者が共有者となると安値での売却を迫られる可能性があるのです。
売却する意志がなければ、無理に買取に応じる必要はありません。
しかし拒否し続けると、新たな共有者から「共有物分割請求」をされる可能性があります。
共有物分割請求とは、共有状態の解消を求める手続きです。
買取に応じないなど共有解消の話し合いが進まない際に、裁判所に申し立て解決を目指します。
共有分割請求の手続きは、まず調停によって話し合いでの解決を図りますが、そこで合意に至らなければ、裁判所が審判を行い、最終的な判断を下します。
建物の場合、最終的にどちらの共有者が相手の持分を買い取って単純所有にするか、競売で売却し、その売却代金を共有者同士で分割することになるケースが多いでしょう。
共有分割請求されると、共有の解消は避けられず不動産を手放さなければならない可能性もあります。
さらに、調停や訴訟に労力もかかるので、共有者に大きな負担となる恐れがあるでしょう。
共有者が借金を滞納すれば即差押えになるわけではなく、一定のステップを踏んで差押えまで進みます。
ここでは、差押えまでの具体的な流れをみていきましょう。
滞納1~2回目は、電話やはがきによる催促が来るのが一般的です。
しかし、催促を無視し滞納を続けていると、督促状・催告書が届きます。
催告書には支払い期限までに対応しないと法的手続きをとる旨が記載されており、これを無視すると期限の利益喪失通知が送付されます。
期限の利益とは、分割払いができる権利です。
期限の利益を喪失すると分割払いできなくなるので、返済の一括請求が行われます。
延滞する債務によって期間は異なりますが、住宅ローンでは滞納から5~6ヵ月ほどが目安でしょう。
住宅ローン滞納のケースでは、一括請求に応じずにいると保証会社が残債を返済する代位弁済が行われます。
しかし、保証会社が肩代わりしてくれるのではなく、代位弁済後は保証会社から一括返済の請求がくるだけです。
なお、税金滞納のケースでは期限の利益喪失通知・一括返済請求の手順はなく、催告書に対応しないと差押えがスタートするので注意しましょう。
不動産を担保としない借入では、差押えにあたり債務名義の取得が必要になるので、事前に法的措置の予告が送付されます。
一方、不動産を担保としている借入や税金は、すぐに差押えの予告が送付されるので注意しましょう。
債務名義を取得するケースでは、債権者から手続きの申し立てがあると債務者にその旨の通知が送付されます。
この通知を無視した場合、あるいは通知に対応しても敗訴した場合は、債務名義が発行され差押えとなります。
差押えが決定すると、競売開始決定通知が送付されます。
通知後は、裁判所の執行官による現況調査が行われ、期間入札決定通知により、入札の期日が通知されます。
送付後は期日に従って競売が開始され、落札者が新たな所有者となるのです。
落札後、代金が支払われると所有権は強制的に落札者に移転され、前の所有者は立ち退きしなければなりません。
住宅ローンや民間の借金を延滞した場合、滞納から立ち退きまでは1年半〜2年ほどでしょう。
税金滞納はより差押えまでの期間が短く、滞納額や税金・自治体によっても異なりますが、2ヵ月ほどで差押えが完了するケースもあるので注意しましょう。
共有不動産が差押えにあうと、自分の持分にも影響が出るため適切な対処が重要です。
ここでは、共有不動産の差押えに対する対処法として「所有し続ける」と「手放す」の2つに分けて解説します。
愛着のある不動産や自宅などでそのまま住み続けたいなら、以下のような対処方法が検討できます。
差押え前であれば、差押えられる前に持分を共有者から購入する方法があります。
滞納している共有者の持分は、差押え前であれば買取可能です。
持分を共有者から買い取ることで、共有者の持分はなくなり差押えの対象からも外れます。
また、持分を買い取って単独名義にできれば、活用や売却は自分の意思で自由にできる点もメリットです。
ただし、共有者との関係性によっては売買に合意してくれない可能性もあり、そもそも買い取るだけの資金も必要になります。
共有者間の売買だからといって相場よりも極端に安値で買取ると、みなし贈与として贈与税が課税される恐れがあります。
どれくらい安くすると贈与税が課税されるかは判断が難しいので、専門家に相談するとよいでしょう。
なお、差押え目前で売買を行うと、債務者が資産を減らす目的で売買したとみなされ、売買が取り消される恐れがあるので注意が必要です。
共有者の未払いが解消されれば差押えされることはありません。
そのため、いったん自分で債務を肩代わりし完済するのも有効です。
この場合は、完済後に共有者に弁済分を返還請求することになります。
しかし、弁済できるだけの資金力が必要になり、仮に弁済しても延滞していた共有者が返還請求に対応できるかは疑問が残るところです。
共有者とのトラブルに発展するリスクもあるので、借用書を取り交わすなど慎重に対応するようにしましょう。
すでに差押えになっているなら、競売に参加し落札する方法が検討できます。
落札できれば持分は自分のものとなるので、単独名義にできる可能性もあります。
しかし、入札者が他にいると確実に落札できるわけではない点に注意が必要です。
基本的に、競売物件を購入する人は安値での落札を検討しています。
また、落札者に業者がいるケースでも、少しでも安値で落札しようとするので、思い切って高値をつければ落札できる可能性があるでしょう。
共有不動産を手放してもいいなら、以下のような方法が検討できます。
差押え前であれば不動産の売却を視野に入れるとよいでしょう。
共有不動産は単独での売却はできませんが、共有者全員の合意があれば不動産全体の売却が可能です。
共有者全員が合意すれば、通常の不動産と同じように同様に売却できるため、市場価格での売却が期待できます。
滞納している共有者も売却金で借金を解消できるメリットがあるため、売却に応じてくれる可能性があるでしょう。
ただし、持分の売買同様、差押え目前では売買が取り消される恐れがあるので注意が必要です。
また、住宅ローン滞納のケースでは住宅ローンが完済できなければ売却ができません。
この場合は、金融機関の合意を得て売却する「任意売却」を検討するとよいでしょう。
破産管財人とは、自己破産した際に破産者の財産を管理する人です。
破産手続き時に裁判所から選任され、一般的には弁護士が選ばれます。
破産管財人は破産者の資産を換金して債務者に配当する役割を担うため、破産者の持分の売却が可能です。
すでに共有者が自己破産の手続きを行い、破産管財人が選任されているなら相談し、不動産全体の売却を検討するとよいでしょう。
また、破産管財人側から売却の申し出を受けるケースもあります。
共有者との関係性が悪く、話し合いに応じてくれない・今後関わりたくないなら、自分の持分の売却を検討するのもよいでしょう。
自分の持分であれば、共有者の合意なく単独で売却できます。
また、差押えの対象でもないので、共有者が差押え目前であっても問題なく売却可能です。
しかし、持分のみは買い手にあまりメリットがないので、仲介では買い手がつかない恐れがあります。
持分のみでの売却を検討するなら、専門の買取業者を検討するとスムーズに売却できるでしょう。
共有名義の不動産が差押えられたときの適切な対処法は、不動産の状況や滞納状況・差押えまでのタイミングなどによっても異なります。
とにかく共有者との関係を早く解消したいからといって、安値で売却したり、共有者の持分を高い価格で買い取ったりすると、結果的に損をしてしまう可能性があります。
共有状態の不動産や差押えのトラブルで悩んでいるなら、専門家や関係者に相談しながら適切な解決策を探すことをおすすめします。
共有者が差押えにあるだけでなく、自分の未払いにより持分が差押えにあうケースもあります。
自分の持分が差押えにあうと共有者にも迷惑がかかるので、早めの対策が必要です。
ここでは、自分の持分の差押えを防ぐための対策として、以下の3つを紹介します。
任意売却とは、債権を持つ金融機関の合意を得て不動産を売却する方法です。
抵当権が設定されている不動産は、ローンを完済し、抵当権を抹消しなければ売却できません.。
しかし、任意売却であれば、特別に抵当権抹消の許可を得て抵当権を抹消し、売却することが可能です。
また、任意売却は、金融機関の合意が必要という点以外は、通常の不動産売却と同じように行えるため、競売よりも柔軟で高値の売却が期待できる点もメリットです。
ただし、金融機関との交渉が必要になるので、不動産会社の担当者に同席してもらうなど金融機関が納得できるような対策が必要になります。
任意売却できる期間は競売入札開始までとなるので、できるだけ早い段階で不動産会社に相談しましょう。
差押えされそうな状況は他の共有者にも伝えておくことが重要です。
そのうえで、他の共有者に売却し名義変更を検討するとよいでしょう。
差押えられると共有者にもデメリットが生じることを伝えると、名義変更に合意してくれる可能性があります。
自分の持分のみなら単独で売却できるので、差押え前であれば売却を検討するとよいでしょう。
ただし、差押えまでのタイミングによっては売買が無効になる点は注意が必要です。
また、持分のみの売却は仲介では難しいため、専門業者への売却を検討することをおすすめします。
買取であれば短期間での売却ができるので、差押えまで猶予がない状態でも売却による問題解決を目指しやすいでしょう。
こちらもタイミングによっては契約が取り消しになるので、不動産会社だけでなく弁護士への相談をおすすめします。
弁護士と提携している専門業者であれば、適切なサポートをうけスムーズな売却が期待できるでしょう。
共有者が借金を滞納し差押えにあうと、自分の持分に影響はないとはいえ、競売後に第三者が共有者に加わり、賃料を請求される・買取を迫られるなどのリスクが生じます。
リスクを回避するには、持分の買い取りや債務の弁済・競売で入札などが検討できますが、いずれも資金や手間が必要です。
共有者の差押えに巻き込まれたくないのであれば、自分の持分の売却を検討するとよいでしょう。
訳あり不動産相談所では、共有持分の売却にも対応しています。
士業とも連携しており法的な問題の解決を含め売却全体をサポートできるので、共有持分で悩んでいる方はお気軽にご相談ください。
この記事の担当者