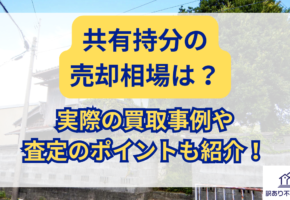
共有持分の売却相場は?実際の買取事例や査定のポイントも紹介!
詳しく見る

共有持分権とは、複数の所有者が存在する不動産に付随する権利の名称です。
共有持分の不動産の活用は、共有者からの同意がないことには始まりません。
建て替えや増改築を行いたい場合には、共有者全員の同意が必要不可欠です。
共有者の数が多ければ多いほど、手間がかかるのは否めません。
ここでは、共有持分権の内容やメリット・デメリット、売却の方法について解説します。
目次
共有持分権とは、1つの不動産に対して共有者それぞれが保有している権利を指します。
共有とは、2人以上で建物や土地を所有している状態です。
3人の名前が登記事項証明書(または登記簿謄本)に記載されていれば、共有者は3名となります。
共有者ごとのそれぞれの所有権の割合が共有持分です。
たとえば、配偶者と子2人が相続人であり、遺産分割協議にて「共有分割」を選択した際には、次の共有持分が適用されます。
| 相続人 | 共有持分 |
|---|---|
| 配偶者 | 2分の1 |
| 子A | 4分の1 |
| 子B | 4分の1 |
※遺言書が存在しない場合の法定相続分です
| 分割方法 | 内容 | 特徴 |
|---|---|---|
| 現物分割 | 相続人の数に応じた分割 ※相続人2人⇒2分の1 ※相続人3人⇒3分の1 | ・相続人全員に公平な分割が可能 ・相続人ごとの相続税の負担を軽減 ・測量費用などが生じる可能性がある |
| 代償分割 | 相続人のうち1名が土地の所有者になる 他の相続人には現金にて分割 | ・相続人全員に公平な分割が可能 ・土地をそのままの形で残せる ・不動産評価額を算定する必要がある |
| 換価分割 | 土地の売却時に得た売却金額を 相続人全員で均等に分ける | ・相続人全員に公平な現金での分割が可能 ・売却の際に所有権移転登記が必須となる ・売却金額によっては譲渡所得税の納付も |
| 共有分割 | 相続人の全員で土地を共有する ※特定の所有者を決定しない | ・土地をそのままの形で残せる ・相続人全員が承諾しないと売却できない |
共有名義とは、不動産の所有者が2人以上存在するという状況です。
共有持分権とは、共有者が有する権利を指します。
| 内容 | |
|---|---|
| 共有名義 | 不動産の所有者が2人以上存在するという状況 |
| 共有持分権 | それぞれの共有者が有する権利 |
| 共有持分 | 共有者ごとの不動産の所有権の割合 |
共有持分が生じる原因の代表的なものは、相続とペアローンです。
相続の際、共有分割を選択した場合、共有持分が発生します。
不動産の購入時にペアローンを設定した際にも、出資額に応じた共有持分が生じる形です。
また、アパート1棟などを共同購入した場合も、出資額ごとの共有持分が設定されます。
そして、私道に面して建てられている複数の住宅および敷地に対する私道持分も、共有持分の一種です。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 共有型私道 | 1つの私道に対して、複数人が均等に所有3人の所有者であれば、3分の1ずつの私道持分 |
| 持合型私道 | 1つの私道に対して、複数人が分筆所有権登記をした状態 ※敷地に接する部分のみなど ※私道全体への通行地役権設定が必要 |
共有持分は、不動産登記事項証明書の「権利部(甲区)(所有権に関する事項)」「権利者その他の事項」にて確認可能です。
たとえば、共有者が3名の場合、持分3分の1などの形で記載されます。
共有持分は土地と建物両方に記されるため、見落とさないように注意しましょう。
ここからは、共有持分権のメリットおよびデメリットを紹介します。
メリットとデメリットの両方を比較することで、共有持分の不動産の活用のヒントになれば幸いです。
共有持分権が有するメリットは次の2つです。
夫婦でペアローンを設定した際、夫婦それぞれが住宅ローン減税の対象となります。
住宅ローン減税とは、最大13年間に渡り、毎年末の住宅ローン残高の0.7%または1.0%相当が所得税より控除される制度です。
また、共有持分の不動産を売却した場合、不動産譲渡所得より最大3,000万円の所得控除が受けられる可能性があります。
相続時に不動産の共有分割を選んだ際には、共有持分ごとの相続税が課せられます。
相続税評価額4,000万円の土地を共有分割した場合、次の評価額が課税対象です。
| 相続人 | 共有持分 | 相続税課税対象額 |
|---|---|---|
| 配偶者 | 2分の1 | 2,000万円 |
| 子A | 4分の1 | 1,000万円 |
| 子B | 4分の1 | 1,000万円 |
共有持分権には所得税の控除などのメリットを有する一方で、以下の2つのデメリットが生じるリスクがあります。
共有持分の不動産は、共有者全員の同意が得られない限り、売却が認められません。
売却の他にも、建て替えや増改築も共有者全員の同意が求められます。
| 活用事例 | 活用条件 |
|---|---|
| 共有持分の不動産を賃貸物件にする | 過半数の共有者からの同意 |
| 共有持分の不動産を売却する | 共有者全員の同意 |
| 共有持分の土地部分への建築 | 共有者全員の同意 |
| 共有持分の建物の建て替え | 共有者全員の同意 |
| 共有持分の建物の増改築 | 共有者全員の同意 |
ただし、専門の不動産業者への共有持分のみの売却は可能です。
相続などで引き継いだ共有持分不動産の早期現金化を図りたい方は、専門の不動産業者に相談することをおすすめします。
共有持分の不動産は、年月を経るごとに共有者が増加することを想定しておきたいところです。
仮に共有者Aが亡くなった場合、共有者Aの配偶者や子や孫、父母や祖父母のいずれかが共有者へと代わります。
そのため、共有者同士の面識がない、共有者と連絡が取れないなども、あり得ない話とは言い切れません。
共有持分不動産は建て替えや増改築の際、共有者全員の同意が必須条件です。
築50年超の不動産であれば、倒壊や火災のリスクも生じるため、共有者との関係を良好に保つことがトラブル回避のコツと言えるでしょう。
不動産の共有持分権は、民法にて定められた権利です。
「共有物の使用」には、共有者が共有名義不動産を共有持分に則った使用ができることが記されています。
ただし、持分割合を超過した使用については、他の共有者へ然るべき費用を支払う義務が生じる点は注意が必要です。
「共有物の変更」では、共有名義不動産に変更を加える際には、他の共有者の同意が必須であることがわかります。
「共有物の変更」に該当するのは、主に以下の項目です。
民法第252条「共有物の管理」では、共有名義不動産の管理行為について記されています。
たとえば共有持分の不動産を賃貸物件にする際には、共有者の過半数からの同意が不可欠です。
裁判所が認めた場合に限り、次の共有者を除いた管理行為を実行できます。
ちなみに、雨漏りの補修などに関しては「保存行為」に該当するため、他の共有者からの同意は必要ありません。(民法第252条5項)
主に以下の項目が、共有者の過半数からの合意によって決められます。
つまり、共有者同士の関係性を良好に保つことが、共有持分不動産の活用には必須ということです。
共有持分の不動産は、共有者全員の同意が得られないと売却ができません。
ただし、共有持分のみを売却することは可能です。
ここからは、共有持分の売却方法と注意点を紹介します。
共有持分のみの売却に限り、他の共有者からの同意は不要です。
他の共有者もしくは、専門の不動産業者が共有持分の売却先の候補となり得ます。
ただし、他の共有者への売却は、一定以上の資金を用意できることが条件です。
まずは、他の共有者に相談することから始めてみましょう。
他の共有者への売却のメリットは、相場に則った売却価格が期待できる点です。
相場価格が2,000万円、共有持分4分の1の土地の場合、2,000万円÷4=500万円で売却できる可能性があります。
専門の不動産業者への売却の場合、相場よりも割安になる傾向がありますが、確実に共有持分を処分したい方におすすめです。
共有者の所在が明らかでない共有持分を裁判所を通して売却するためには、以下の4つのパターンのいずれかに該当することが条件です。
所在等不明共有者の持分の取得は、共有名義不動産を単独所有したい方に向いている方法です。
所在が不明な共有者の持分の買取が可能です。
所在等不明共有者の持分の譲渡は、所在が明らかでない共有者と自身の持つ共有持分を合わせて第三者に対して売却できる制度です。
ただしあくまでも、裁判所は売却の権利を認めるだけであり、売却活動については共有者自身が行う必要があります。
不在者財産管理人選任は所轄の家庭裁判所に申立後、所在が不明な共有者の代理として不在者財産管理人を選ぶ方法です。
失踪宣告は、共有者の生死が7年以上わからない場合に適用される制度です。
こちらも所轄の家庭裁判所への申立が必要となります。
共有者の全員から同意を得て、共有名義不動産全体を売却できた際には、所轄の法務局への所有権移転登記が求められます。
共有持分の売却の場合には、共有持分移転登記も合わせて行うことが必須です。
共有持分移転登記は、以下のパターンに該当する方が対象となります。
共有持分移転登記では、共有者全員の印鑑登録証明書があることが前提条件です。
「登記の目的」には、どの共有者からどの共有者に対して、どの程度移転したのかを記載します。
| 記載する内容 | |
|---|---|
| Aの持分すべてをBに移転 | A持分全部移転登記 |
| Aの持分の一部をBに移転 | A持分一部移転登記 |
相続時は、共有持分権が発生しやすいケースです。
遺産分割協議にて共有分割を選んだ際には、対象となる相続人(配偶者や子や孫、親や祖父母など)に共有持分が設定されます。
遺言書が存在する場合には、遺言書の内容が優先されますが、法定相続分を基にした共有持分が一般的です。
2024年4月1日より、不動産の相続登記申請の義務化が施行されています。
不動産を相続した方(相続人)は、所轄の法務局にて所有権移転登記を済ませることが必須です。
単独名義で不動産を相続した方はもちろんのこと、共有名義の場合にも相続登記は求められます。
共有持分のみの相続登記もあり得るため、該当する方は、不動産の登記事項証明書を確認しておくと良いでしょう。
共有持分の一番のリスクは、活用に至るまでが厄介な点です。
共有持分不動産の活用は、共有者全員または共有者の過半数からの同意が前提条件となります。
たとえば老朽化に伴う建て替えを希望する際には、共有者のうち一人でも反対者がいれば建て替えは法的に認められません。
他にも、時間の経過とともに共有者が増加する、あまり面識のない人が共有者となるケースも考えられます。
相続時に共有状態を避けるためには、遺産分割協議にて「代償分割」を選ぶのが現実的かと思われます。
代償分割とは、相続人のうち一人が相続不動産の所有者となり、他の相続人には相場相当の現金を公平に分割する方法です。
相続税路線価や固定資産税評価額を基に相場を算定します。
より正確性を増したい場合には、不動産鑑定士に依頼するのがおすすめです。
共有持分を解消する方法として、次の5つの方法が挙げられます。
それぞれの特徴を踏まえた上で、最適な選択のための参考になれば幸いです。
他の共有者に共有持分を売却することで、共有持分の平和的な解消が可能です。
この際の共有持分の価格は、相場価格に準じた金額が望ましいかと思われます。
共有持分を増やしたい共有者が存在する場合に向いている方法です。
共有名義の不動産を、共有持分に応じて分筆する方法です。
比較的広大な土地や、総戸数の多め(10棟以上など)の集合住宅などでの選択肢となり得ます。
測量費用が発生する可能性があるため、事前に負担割合を決めておくと良いかもしれません。
共有持分の解消には、裁判所への共有物分割請求訴訟も挙げられます。
裁判所に認められた際には、現物分割や代償分割や換価分割のいずれかにて、共有者に現金などが分配される形です。
この場合の換価分割は競売が伴うため、現物分割または代償分割を提案後、成立しなかった場合に限り、換価分割に進むことが民法第258条に記載されています。
ただしあくまでも、共有者同士の話し合いが基本であり、共有者分割協議で解決しなかった際に共有物分割請求訴訟が選択肢になると捉えておいたほうが無難です。
共有持分は、第三者への売却が可能です。
とはいえ、中々買い手が見つからないということも考えられるので、専門の買取業者に依頼することをおすすめします。
また、後々のトラブルを回避するために、あらかじめ共有持分を売却することを他の共有者に話しておきましょう。
共有持分の放棄は、民法第255条「持分の放棄及び共有者の死亡」にて認められています。
他の共有者からの同意は不要ですが、協力が必要となる点は注意したいところです。
共有持分の放棄には、所轄の法務局への持分移転登記が求められます。
放棄された共有持分は、他の共有者に帰属される形です。
共有持分の放棄は、他の共有者に「放棄の意思」を示すことから始まります。
登記申請には、他の共有者からの協力が不可欠です。
放棄した共有持分の評価額によっては、贈与税の対象(みなし贈与)となる点には注意しましょう。
持分放棄の場合、共有者全員の住民票や本人確認書類の提出が求められます。
持分移転登記で必要な書類などは以下のとおりです。
| 必要書類等 | 内容 |
|---|---|
| 登記申請書 | 所有権移転登記の申請書類。 法務局のサイトより入手可能。 |
| 登記原因証明情報 | 登記に至るまでの原因もしくは、法律行為を記した書類。 原因:相続 法律行為:持分放棄 (※共有持分放棄の場合) |
| 登記識別情報 | 所轄の法務局より、新たに不動産の登記名義人となった申請者に通知される 12桁の英数字が記された書類。 |
| 固定資産評価証明書 | 不動産(土地、建物)の固定資産評価額を証明する書類。 物件の所在する市区町村役場にて入手可能。 |
| 住民票 | 持分放棄をする方以外の共有者(登記権利者)の住民票。 各々の住所地の市区町村役場にて入手可能。 |
| 印鑑証明書 | 共有持分を放棄する方(登記義務者)の印鑑証明。 住所地の市区町村役場にて入手可能。 |
| 本人確認書類 | 不動産の共有者全員の本人確認書類。 運転免許証などの写しが該当。 |
| 印鑑 | 共有持分を放棄する方(登記義務者)および他の共有者(登記権利者)の印鑑 登記義務者:実印 登記権利者:認印 |
| 委任状 | 委任者本人が作成した委任状。 遠方に住んでいる人が持分放棄する際に使用。 |
| 登録免許税 | 所有権移転登記や持分移転登記の際、法務局窓口に収入印紙にて納める税金。 登録免許税=不動産価格×持分割合×2% (※持分移転登記の場合) |
共有持分権を所有する方には、次の税金や費用が発生します。
アパートなどで不動産収入を得ている場合には、経費として計上可能です。
固定資産税はその年の1月1日時点で、不動産を所有している方に課せられる税金です。
都市計画税は、市街化区域内の土地や建物が課税対象となります。
共有持分の不動産の場合には、持分割合の最も高い共有者宛に、固定資産税や都市計画税の納付書が届くのが一般的です。
あらかじめ、共有者同士の負担割合を決めておくと、スムーズに納付できるでしょう。
設備の修繕などでかかる費用です。
こちらも、負担割合を設定することで、共有者の一人だけに負担がかからないような工夫をすることが求められます。
不動産の価値を高める目的で計上される費用です。
バリアフリー化や、断熱機能の向上などが挙げられます。
助成金制度の対象になるものも存在するため、興味のある方は、調べておくと良いかもしれません。
共有名義の不動産で発生する電気代やガス代、水道料金が該当します。
共有者が居住しているか否かで負担割合も変わるため、事前に取り決めをしておくと、トラブルの回避につながります。
共有持分の売却先の候補となり得るのは、他の共有者もしくは専門の不動産業者です。
ここでは、不動産業者への売却を例とした流れを紹介します。
なお、共有持分のマンションの売却については、下記関連記事の「共有名義のマンションを売却する方法」もご覧ください。
関連記事:共有名義のマンションを売却する方法|マンション売却相談センター
まずは、共有持分の買取を実施中の不動産業者に問い合わせをします。
取引実績などから、複数の業者をピックアップしておくと良いでしょう。
担当者の現地訪問の後、見積額が提示されます。
見積額や各種条件が合致するものであれば、売買契約へと進みます。
買取の場合には、早ければ1ヶ月ほどで売買契約が成立する形です。
所轄の法務局にて所有権移転登記を済ませたら、売却の完了となります。
不動産を売却した年の翌年には、所得税の確定申告を行います。
売却価格-取得費-譲渡費用-特別控除額=不動産譲渡所得
不動産譲渡所得がマイナス(損失)となった際には、確定申告は不要です。
ただし、他の所得(給与所得や事業所得など)と損益通算されるケースもあるため、念のために確定申告をしておいたほうが良いかと思われます。
所得税や住民税の還付が受けられるかもしれません。
ここまで、共有持分権の内容やメリットとデメリット、売却方法について紹介してきました。
共有持分は、共有者同士の関係性に大きく左右されます。
良好であれば問題は生じませんが、共有者が変わる、増えるタイミングでトラブルとなる可能性もあります。
共有持分の解消には、売却も選択肢のひとつです。
共有持分にお困りの方は、訳あり不動産相談所にお問い合わせください。
この記事の担当者

担当者③