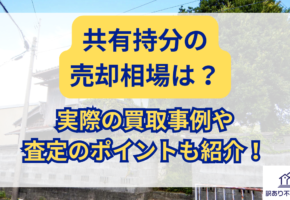
共有持分の売却相場は?実際の買取事例や査定のポイントも紹介!
詳しく見る

「共有不動産だけど別居中に売却できる?」「離婚を検討しているけどいつ売却した方がいい?」
別居中や離婚検討中は不動産の売却タイミングに悩む方も少なくありません。
特に、家が共有名義だと売却には他の共有者の同意が必要で、自分ひとりの判断で売却を進めることはできません。
共有者(配偶者)とのトラブルに発展する恐れもあるため、慎重な判断が必要です。
この記事では、別居中の共有不動産の売却方法やポイント・売却しないリスクなどを分かりやすく解説します。
目次
離婚に伴う家の処遇はトラブルになりやすい大きな問題です。
とくに共有不動産は単独名義の不動産に比べ取り扱いが難しくなります。
共有不動産とは、不動産の名義(所有権)が複数人で共有されている状態です。
結婚後に夫婦で住宅ローンを組んで家を建てた場合などに、共有不動産となるケースがあります。
売却に適したタイミングは、資産状況などによって別居中か離婚後かに分かれます。
ここでは別居中と離婚後、それぞれに適したケースについて解説します。
離婚時には婚姻後に築いた財産を夫婦で分割する財産分与が行われます。
財産分与では一般的に夫婦で2分の1ずつ分割するのが原則となり、共有名義の家も財産分与の対象です。
しかし、財産の大半が共有名義の家であれば分割が難しくなるため、別居中に売却した方がスムーズに財産分与を進められます。
例えば、共有名義の家2,000万円と現預金400万円があるケースをみてみましょう。
公平に2分の1ずつ財産分与するなら、夫婦の取り分は夫1,200万円、妻1,200万円となります。
ところが、家を売却しない場合、家を取得した方は取得額が2,000万円となるため、取得しない方に800万円の代償金を支払う必要があるのです。
家を取得した方は代償金を支払ううえに現預金は取得できなくなってしまうため、その後の生活が苦しくなる恐れもあるでしょう。
そのため、どちらが家を取得するかでトラブルになりやすいのです。
別居中(離婚前)に家を売却しておくことで、現金で平等に分割できます。
代償金の支払いや現預金が取得できないといったことも発生しにくいため、トラブルを避けやすくなるでしょう。
住宅ローン残債がある家を離婚後も所有していると、もちろん住宅ローン残債の支払いが続きます。
家が夫婦の共有名義である場合、ペアローンを組んでいる・収入合算しどちらかが連帯保証人または連帯債務になっているかのいずれかのケースが多いです。
この状況で離婚時に住宅ローン残債が残っていると、どちらかが返済できない場合、もう片方は返済できない方の債務を負担しなければならないリスクがあります。
とくに、家に住まない方が住宅ローンの返済を滞らせる可能性が高く、住む方もそのリスクを心配しながら生活するのはストレスになりかねないでしょう。
また、離婚にともない住宅ローンをどちらかの名義で一本化するにしても、一本化するほうにそれなりの収入がなければ認められません。
そもそも夫婦二人の収入で住宅ローンを組んでいた状況から考えると、どちらか1人に返済が偏ると返済が難しくなることが予測できるでしょう。
住宅ローン残債を離婚後も夫婦で返済し続けるのは、返済が滞るリスクが大きくなります。
関係性によっては離婚後に住宅ローンの支払いで連絡を取ることがストレスになるケースもあるでしょう。
離婚前の別居中の段階で売却し住宅ローンを完済しておくことで、離婚後に住宅ローンの返済トラブルが発生するのを防げます。
一方で、住宅ローンを完済していれば、売却金を離婚後の財産分与で分ける方が税制上有利になります。
財産分与は贈与にあたらないため贈与税は課税されません。
一方、離婚前に売却し売却金を分けた場合、状況によっては贈与とみなされ贈与税が発生する恐れがあります。
贈与税が課税されると税率は最大55%と税負担が大きくなるため、財産分与で非課税で分割したほうがお得と言えるでしょう。
また、住宅ローン完済済みであれば、焦って売却する必要がないというのも大きなメリットです。
住宅ローン残債がある場合離婚までに売却した方がよいため、売却期間に余裕がなく売り急ぐケースもあります。
その点、完済しているなら慎重に売却を進められるため、離婚後の条件の良い売却タイミングで高値で売れる可能性もあるでしょう。
共有名義の不動産を売却する場合、共有者全員の合意がなければ不動産全体を売却できません。
しかし、自分の持分だけであれば共有者の合意なく売却できます。
別居中という場合、共有者に合意を得るのが難しい場合もあるので、持分のみの売却を検討するのも1つの手です。
とはいえ、共有持分のみの売却はトラブルにもなりやすいので注意しましょう。
ここでは、できるだけトラブルを避けて共有不動産を売却する方法を紹介します。
共有持分だけでも売却できますが、第三者に持分を売却するのは現実的ではありません。
持分だけ購入しても不動産の活用は難しく、そもそも他人が共有者になるのに買いたいという買主もいないでしょう。
スムーズに売却するなら、やはり共有者に合意を得て不動産全体を売却する方法が一番です。
不動産全体であれば買い手が現れやすく、高値での売却も期待できるでしょう。
財産分与を平等に行うためや持分だけで売却するリスクなどを伝えると、共有者も合意してくれる可能性があるので、まずは説得することをおすすめします。
どうしても合意を得られない場合、持分の売却として以下の2つの方法が検討できます。
共有持分は第三者への売却は難しいですが、共有者なら購入するメリットがあるため買い取ってくれる可能性があります。
共有者が買い取れば、単独名義になるため購入後に住む・売却するなど活用もしやすいでしょう。
ただし、買い取ってもらう際の価格には注意が必要です。
家族だからと相場よりも極端に安値で売却すると、贈与とみなされ贈与税が課せられる恐れがあります。
たとえば、市場で3,000万円で売却できる家の2分の1の持分であれば、単純に計算すれば1,500万円の価格です。
これを300万円で売却すると、1,200万円を相手に贈与したとみなされる可能性があります。
価格を決める際には相場に対して適切な価格でなければトラブルになりやすいので、プロに相談することをおすすめします。
また、そもそも相手方に持分を買い取る資金がなければ成立しない点にも注意しましょう。
共有持分のみの売却は取り扱っていない不動産会社も少なくありません。
しかし、共有持分を専門的に買い取る業者もいるので、持分のみを売却するならそのような業者を検討するとよいでしょう。
持分のみの売却であれば、共有者の合意を得ずに単独で売却できます。
ただし、合意を得る必要がないとはいえ、勝手に売却を進めるとトラブルにもなりかねません。
持分のみを売却する場合でも、共有者には一度話をしておくことをおすすめします。
共有不動産は単独名義の不動産より売却が難しいため、押さえておきたい注意点もいくつかあります。
ここでは、共有不動産売却で押さえておきたいポイントとして、以下の3つを解説します。
前述の通り、共有名義の不動産全体を売却するには共有者全員の同意が必要です。
共有者の同意なく単独で不動産全体を売却できないので注意しましょう。
たとえ、共有者が別居中・離婚後であっても共有者である以上は同意を得なければなりません。
仮に、共有持分が夫8・妻2のように偏っている場合でも、多い方が勝手に売れるわけではない点にも注意しましょう。
同意なしで売却した場合、損害賠償請求される恐れもあります。
共有者の合意を得られない場合でも、自分の持分だけを売却することは可能です。
土地であれば共有持分を分筆して売却することが検討できるでしょう。
分筆してしまえば、その分は自分の土地となるので通常の土地と同様に売却できます。
しかし、建物は共有持分のみを第三者に売却するのは難しくなります。
持分のみを売却するなら、前述の通り第三者ではなく「共有者」か「専門の買取業者」を選択したほうがスムーズに売却できるでしょう。
資金に余裕があるなら共有者の持分を自分で買取って単独名義で売却する方法もあります。
共有持分を売却する際には、以下の点には注意が必要です。
共有持分の売却では、売却後に共有者に迷惑がかかってしまう可能性があります。
これは、売却した第三者が共有持分分割訴訟を起こすといったことが考えられるでしょう。
共有持分分割訴訟とは、裁判所を通じて共有状態の解消を図る手続きです。
共有持分を第三者に売却した場合、購入した第三者が共有者に持分の売却や購入を迫る可能性はゼロではありません。
購入した第三者も持分のままでは活用が難しいため、自分の持分を共有者に売却するか・共有者の持分を買い取った方が活用しやすくなるからです。
第三者と共有者で話し合いで解決できない場合、第三者は共有持分分割訴訟を起こす可能性があります。
このように売却後に購入者と共有者でトラブルになるケースがあるため、共有持分のみを売却する場合でも共有者に了承を得ておくことをおすすめします。
別居中に不動産を売却した方がよいケースであっても売却が難しいケースもあるので、状況を把握し慎重に判断することが大切です。
ここでは、別居中の不動産売却が難しいケースを紹介します。
共有不動産は共有者の同意がなければ売却できません。
同意を得られない場合は不動産全体での売却はできないため、持分のみの売却を行うことになります。
住宅ローン残債が売却額を上回っている状態をオーバーローンといいます。
オーバーローンの場合、抵当権が抹消できないため売却できません。
抵当権とは、住宅ローンを組む際に金融機関が設定する権利です。
抵当権の抹消には住宅ローンの完済が必須となるため、売却しても住宅ローンが完済できない場合は売却できないのです。
ただし、売却額だけで完済できない場合でも、自己資金などで補填して完済できるのなら売却できます。
売却前に住宅ローン残債の正確な額と査定額・自己資金状況を把握して、慎重に売却を判断しましょう。
共有不動産を売却すると税金や費用が発生するため、事前にどれくらいかかるかシミュレーションしておくことも大切です。
売却額によっては費用や税金を捻出するとマイナスになってしまうケースもあるので注意しましょう。
売却時にかかる主な税金・費用には以下のようなものがあります。
| 種類 | 概要 |
|---|---|
| 印紙税 | 売買契約書にかかる税金 |
| 登記費用 | 不動産登記にかかる登録免許税と司法書士費用 |
| 仲介手数料 | 不動産会社に支払う手数料 |
| 譲渡所得税 | 利益が発生した場合のかかる税金 |
| 住宅ローン完済費用 | 金融機関の一括返済手数料など |
| その他費用 | 測量やハウスクリーニング・引っ越し費用など状況に応じて発生する費用 |
一般的には売却時の費用・税金は、売却額の5~10%といわれています。
たとえば、3,000万円で売却した場合150~300万円の費用がかかります。
費用をあらかじめ考慮していないと住宅ローンが完済できない・思ったよりも手元に残らないとなりかねないので注意しましょう。
共有持分を相手に売却する場合、売却額によっては贈与税が発生します。
前述したように、相場よりも安値で持分を売却すると贈与とみなされる恐れがあり、贈与に該当する場合、基礎控除110万円を超えた部分に贈与額に応じた税率で課税されます。
相手の負担を軽減しようと相場よりの安値で売却すると、相手が思わぬ税負担で苦しむ場合があるので注意しましょう。
また、売却で利益が出ると譲渡所得税が発生します。
譲渡所得税は、家の所有期間にもよりますが売却利益×20.315%または39.63%です。
たとえば、1,000万円の利益が出ると200万円または400万円近くの納税が必要になります。
譲渡所得税が課税されると高額になりがちなので、あらかじめ税額もシミュレーションして納税に備えておくことが大切です。
譲渡所得税には、いくつか特例や控除が設けられており、活用することで節税が見込めます。
代表的な特例には以下が挙げられます。
3,000万円特別控除では、売却の利益(譲渡所得)から3,000万円を控除できるため、譲渡所得3,000万円以下であれば税負担を0円にできます。
また、所有期間が10年を超える家の売却であれば、譲渡所得税の税率を軽減できる特例が10年超所有軽減税率の特例です。
他にも特例や控除は用意されているので、状況に応じて適切な特例を適用することで税負担を軽減できるでしょう。
税金の計算や特例の適用に不安がある場合は、不動産会社や税理士などのプロへの相談をおすすめします。
別居中に共有不動産を売却しないと、以下のようなリスクが生じかねません。
ペアローンや連帯債務の場合、相手の住宅ローン返済が滞ると自分に返済が請求されます。
返済に対応できない場合、金融機関は抵当権を行使し家が競売にかけられる恐れがあります。
別居中に売却せずに住宅ローン残債が離婚後まで続くと、どちらかの返済が滞るリスクが高くなります。
仮に競売となってしまうと、通常の売却よりも売却額が大きく下がるなどのデメリットが生じるため、離婚前に売却しておくほうがよいでしょう。
持分のみの売却なら共有者の合意は必要ないため、離婚後にいつ相手が勝手に持分を売却するとも限りません。
持分を売却されると、見ず知らずの第三者が共有者となりどちらか住むかでトラブルになる恐れがあるでしょう。
また、購入した第三者から持分の購入や売却を迫られるケースも多い点にも注意が必要です。
共有持分のまま離婚してしまうと、自分の持分でない方がどのような活用をされるのか不透明になるリスクがある点には気を付けなければなりません。
どうしても持分のまま離婚する場合は、持分についての取り扱いを離婚時に公正証書として残しておくことをおすすめします。
共有名義の不動産は売却が複雑になりがちです。
スムーズに売却するなら、以下のような準備や対策を行っておきましょう。
共有名義の不動産を売却するなら、信頼できる不動産会社を選ぶことが重要です。
信頼できる不動産会社であれば、共有者との合意形成やトラブルが起きた場合のサポートも期待できます。
不動産会社を選ぶ際には、査定額だけでなく以下のようなポイントをチェックすることも大切です。
総合的に評価して信頼できる不動産会社を選ぶようにしましょう。
また、共有不動産は通常の不動産会社では取り扱っていないケースも少なくありません。
共有不動産などの訳あり不動産を専門的に取り扱う不動産会社を視野に入れることで、スムーズな売却が期待できるでしょう。
共有不動産の売却や離婚に伴う売却はトラブルが発生しやすいものです。
持分の取り扱いや財産分与の割合など、法的なトラブルに発展すると解決にも時間や手間がかかってしまいます。
複雑な問題は自分だけで判断するのではなく、事前に専門家のアドバイスをもらうことでトラブルを避けスムーズな売却が可能です。
不動産会社によっては弁護士などの専門家と連携しているケースもあるので、相談するのもおすすめです。
離婚を視野に入れた別居であれば、別居中に不動産を売却しておくことで財産分与や住宅ローン残債の問題をスムーズに解決できます。
離婚後も住宅ローン財産の残る家を所有していると、差押えのリスクも高くトラブルになりやすいので注意しましょう。
共有不動産を売却する方法には、共有者全員の合意を得るか共有持分のみで売却する方法が挙げられます。
いずれにせよ共有名義の不動産の売却は複雑になりがちなので、専門の業者に相談するとよいでしょう。
訳あり不動産相談所では、共有不動産のような訳あり不動産の売却に際して、経験豊富なスタッフが売却の成功に向けてサポートさせていただきます。
共有名義の売却を考えている方は、まずは訳あり不動産相談所へご相談ください。
この記事の担当者

担当者③