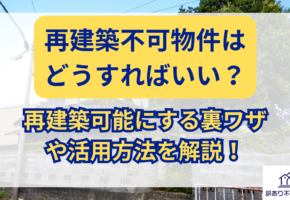
再建築不可物件はどうすればいい?再建築可能にする裏ワザ6選や活用方法を解説!
詳しく見る
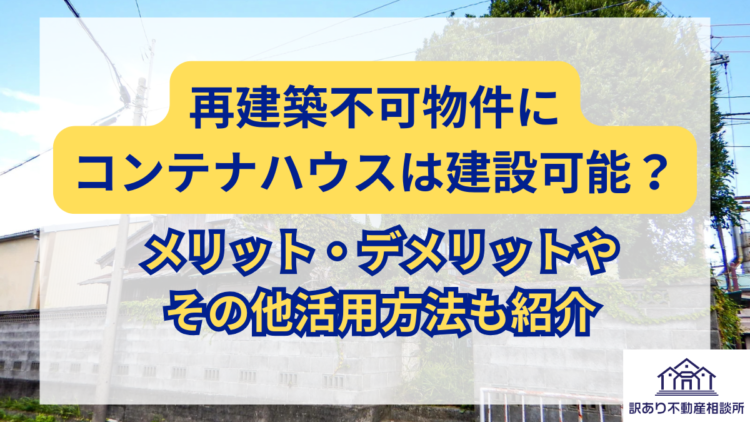
敷地内の新築や増築が制限される「再建築不可物件」は、所有者を悩ませる訳あり物件の一つです。
相続した家が再建築不可物件に該当し、処分または利用法にお困りの方も多いのではないでしょうか。
再建築不可物件には、コンテナハウスを建てるのも一つの手です。
また、そのほかにも様々な手段で再建築不可物件は活用が期待できます。
この記事では、再建築不可物件の概要から、コンテナハウス設置のメリット・デメリット、その他幅広い活用方法に至るまで詳しく解説します。
再建築不可物件の利用・管理にお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
目次
「再建築不可物件」とは、その名の通り建物の再建築ができない物件のことですが、厳密には、既存の建物以外の新築や増築ができない土地を指します。
仮に今ある建物を取り壊して更地にしたとしても、再建築不可物件である土地には家を建てることができません。
すなわち、建て替えも不可ということです。
このように、非常に厳しい制限が設けられている点が特徴ですが、再建築不可物件に該当するのは具体的にどのような土地なのでしょうか。
次の項目で詳しく見ていきましょう。
再建築不可物件となるのは、以下の条件にあてはまる土地です。
それぞれ順番に解説していきます。
「接道義務」とは、建築基準法第42条、および第43条で定められている「土地と道路の距離」に関するルールのことです。
救急車や消防車といった大型車両の進入経路や、災害時の避難経路を確保することを主な目的としています。
接道義務においては、幅員4メートル以上の道路に対し、家の建つ土地が2メートル以上接していなければなりません。
したがって、以下にあてはまる家は、接道義務に違反しているとみなされ、再建築不可物件として扱われます。
このような再建築不可物件が存在する背景には、建築基準法改正の影響があります。
建築基準法は、1950年(昭和25年)に制定されて以降、現在に至るまで幾度も改正を繰り返しています。
その中でも、現在の接道義務は1981年(昭和56年)の改正時に規定されたものです。
したがって、家が建てられた当時は合法だったのに、法律改正後に基準から外れてしまったというケースが多くを占めています。
なお、以上のように建築後の法改正によって基準を満たせなくなってしまった物件のことを、「既存不適格物件」と呼びます。
既存不適格物件は、現行法令に違反して建てられる「違反建築物」とは異なり、基準から外れたからといってそれだけで違法になるわけではありません。
現行の法律規定に沿って居住・活用する分には問題ないのが一般的です。
一部の地域では、「市街化調整区域」に指定されているために、建て替えや新築ができず結果的に再建築不可物件となるケースがあります。
市街化調整区域とは、自然保護・環境保護の観点から、人が暮らすことを前提とした街づくり(市街化)が抑制されている地域のことです。
市街化調整区域にある家の場合、増築や建て替えはもちろん、リノベーションを行う際にも原則として自治体から開発許可を得なければなりません。
なお、ご自身の所有する土地が市街化調整区域にあるかは、各自治体の都市計画課にて確認することが可能です。
再建築不可物件は、利用制限が厳しいものの、活用方法が全くないわけではありません。
たとえば、一般的な居住や内装のリフォーム・修繕などは問題なく行えます。
また、基本的に建物の増築・新築はできませんが、プレハブやコンテナハウスなど、簡易的な物であれば新たに設置することが可能です。
そのほか、駐車場や、農地などへの転用もできるため、敷地内の家が古く、解体せざるを得ない場合でも、ある程度の活用が見込めるでしょう。
なお、住宅ローンに関しては物件の特性上、利用できないケースがほとんどです。
立地条件が非常に優れている、または建物の状態が良好といったアドバンテージが無い限り、基本的にローンは組めないと考えておきましょう。
| 項目 | 可/不可 | 補足 |
|---|---|---|
| 既存建物の利用 | ○ | 内装のリフォームや修繕は可。 建物の大幅な改修、構造が変わるような増改築は不可 |
| 新築 | × | 建築基準法に基づき原則不可 |
| 再建築 | × | 既存建物を取り壊しての建て替えは不可 |
| 簡易的な建築物の設置 | ○ | コンテナハウスやプレハブ、キャンピングカーなど、地面に基礎で固定しない建物は可 |
| 土地売却 | ○ | 売却可能だが、価格が低くなる通常物件に比べて価格が低くなりやすい |
| 土地活用 | ○ | 駐車場やコインランドリーなどに活用可 |
| 公共インフラの利用 | ○ | 既存の水道、電気、ガスを利用する場合は可。 新規の接続は認められない場合がある。 |
| 住宅ローン | △ | 条件次第では可能だが、担保価値が低いため基本的に利用できない |
結論から言うと、再建築不可物件にコンテナハウスを建てることは可能です。
しかし、設置にあたっては様々な条件があるため、すべての再建築不可物件におすすめの方法とは言えないのが実情です。
ここでは、再建築不可物件におけるコンテナハウスの概要からメリット・デメリット、建築時の注意点について解説します。
「コンテナハウス」とは、鉄道や船などでの貨物輸送時に利用される大型の箱(コンテナ)を居住用に改造したものです。
無骨な外観、そして耐久性とカスタマイズ性の高さから近年注目されている建築物の一つと言えます。
堅牢な重量鉄骨造でありながら、一般的な鉄骨造の建物よりも比較的安価かつ短い工期で建築できる点も特徴と言えるでしょう。
コンテナハウスのメリットとして挙げられるのは、主に以下の4点です。
それぞれ見ていきましょう。
コンテナハウスはその独特な佇まいから若者を中心に人気を集めており、近年ではカフェやサロンといった店舗や宿泊施設などにも広く活用されています。
そのため、「自分の店を持ちたいけど、新築コストが気になる」といったクリエイターや個人事業主向けに貸出し、収益化することが可能です。
たとえば大学の周辺など、集客が見込まれる地域に再建築不可物件を所有している場合、コンテナハウスを活用した賃貸は有力な選択肢の一つと言えます。
コンテナハウスのメリットの一つとして、負担の少ない設置・移設が可能な点も挙げられます。
もともと貨物輸送用の容器であるコンテナは、動かしやすさを考慮した設計が特徴です。
基本的には完成したコンテナを現地まで運んで設置するだけのため、建築工事や追加の現場作業がほとんど必要ありません。
移設の際も同様です。
再建築不可物件では、「基礎を地面に固定しない建物」であれば、増築が認められています。
したがって、上記の要件を満たしており、比較的容易に移設できるコンテナハウスは相性がよいと言えるでしょう。
コンテナハウスは耐久力の高さもメリットです。
コンテナハウスと混同されやすい建物として、プレハブハウスがありますが、両者の大きな違いは使用される建材です。
プレハブハウスはもともと物置・倉庫としての利用を想定して作られているため、木造または軽量鉄骨造であることが一般的です。
一方、コンテナハウスはベースとなるコンテナが海上輸送時の過酷な環境にも耐えられるよう設計されているため、より頑強な重量鉄骨造となっています。
したがって、雨風に晒されたり、多少の衝撃を受けたりしても屋内に影響を及ぼす心配がなく、安心して利用できる点が魅力です。
デザイン性の高い建物を利用したい場合にも、コンテナハウスは最適と言えます。
まず、外壁は鉄製であるため、基本的に塗装に使う色を選びません。
無骨な外観を活かしたアースカラーやモノトーンはもちろん、パステルカラーやビビッドカラ―で遊び心や意外性を演出することも可能です。
また、建物がシンプルな長方形のため、屋内でも持ち主の好みに合わせたインテリアを楽しめます。
店舗としての貸出や、趣味の部屋としての活用を考える場合、このような自由度の高さはコンテナハウスならではの魅力と言えるでしょう。
再建築不可物件の活用手段として魅力的なコンテナハウスですが、以下のデメリットがある点に注意が必要です。
メリットだけでなくデメリットもおさえたうえで、コンテナハウスを設置するか検討するようにしましょう。
再建築不可物件でも、基礎を固定しない簡易的な建物であれば基本的に増築が認められています。
しかし、増築できる建物の規模(床面積)が10㎡以下に定められている点に注意が必要です。
10㎡は畳数に換算すると6畳になるため、決して広くはないことがわかるでしょう。
そのため、居住用というよりも、小規模な店舗や、書斎、倉庫としての利用などに用途が限られやすい点がデメリットと言えます。
10㎡以下のコンテナハウスでも、再建築不可物件の所在地域によっては設置できないことがあります。
具体的には「防火地域」および「準防火地域」と呼ばれる、建物の密集度が高いエリアが挙げられます。
人や車の往来が激しい市街地や都市部などは火災発生時の被害が大きいため、火災リスクを防ぐために(準)防火地域に指定されていることが一般的です。
(準)防火地域においては、建築可能な建物の種類が厳しく制限されています。
そのため、コンテナハウスに限らず再建築不可物件自体の活用機会が狭まってしまう点に注意が必要です。
なお、再建築不可物件のある地域が(準)防火地域に該当するかは、所属自治体の都市計画課で確認できます。
再建築不可物件にコンテナハウスを設置するデメリットとして最後に挙げられるのは、初期費用が高くなりやすいことです。
コンテナハウスの費用は状態や種類によって異なり、中古で10万円から手に入るものもあれば、5〜6畳の新設で200万円ほどかかる場合もあります。
安いものは本来のコンテナとしての機能しか備えていないケースが多く、利用に適した設備を自ら整えていかなければなりません。
そうなると、結果的に数百万円以上の費用がかかり、その後の収益による回収が難しくなる可能性があります。
耐久性を考えれば一般的な鉄骨造の建物よりも安価ではあるものの、トータルで見た場合に「安い」とは言えない点に注意が必要です。
再建築不可物件は、コンテナハウス以外にも以下のような活用方法があります。
ご自身の所有する物件や環境に合った方法を選ぶのがおすすめです。
現行法律の基準を満たせば、再建築不可物件を建築可能にできる場合があります。
具体的な方法としては、以下が挙げられます。
| 内容 | 詳細 |
|---|---|
| 「位置指定道路」の申請をする | 所有物件に接道する道が接道義務を果たしているにもかかわらず「私道」であるために道路として認められていない場合、自治体に申請して道路として認めてもらう方法 |
| 隣接する土地を購入/借地して接道義務を果たす | 隣接する土地を購入または借りることで敷地を広げ、接道義務を果たす方法 |
| 隣接する土地と一部を交換する | 隣接する土地と自身の土地の一部を交換することで接道部分の敷地を広げ、接道義務を果たす方法 |
| 自分の敷地をセットバックする | 所有する土地に接する道路の幅が4m未満の場合、自身の敷地を必要分だけセットバック(後退)させることで接道義務を果たす方法 |
| 「43条但し書き道路」の申請をする | 所有物件が道路に接していないものの、大きな私道や公園などがあり一定の通行スペースが確保できる場合、自治体に申請して該当部分を道路として認めてもらう方法 |
基本的にいずれも自治体への申請および近隣住民との交渉が必要なため、時間、費用、労力がかかることは念頭においておきましょう。
特に、申請手続きは複雑になりやすく、必要書類の準備にも時間がかかります。
自分1人では不安という方は、専門家や不動産業者に相談しましょう。
コンテナハウスの代わりにトレーラーハウスを設置する方法もあります。
建物をそのまま地面に設置するコンテナハウスと異なり、タイヤが付いた専用フレーム上に建物を載せているのがトレーラーハウスの特徴です。
建物自体にエンジンが搭載されているわけではないためキャンピングカーのように自走はできないものの、牽引車を利用して容易に動かすことができます。
コンテナハウスは、設置環境や条件によっては「建築物」とみなされ、再建築不可物件に設置できないことがあります。
一方、トレーラーハウスは建築基準法において「車両」扱いになるため、制限を受けにくい点もメリットと言えるでしょう。
ただし、敷地周辺の道路がトレーラーハウスおよび牽引車の進入に十分な広さを有している必要があります。
再建築不可物件となるのは、土地が道路に接していない、または接している道路が極端に狭いといったケースがほとんどです。
したがって、そもそも敷地内にトレーラーハウスを搬入出来ない可能性がある点に注意しましょう。
再建築不可物件でも、一般的な車両が出入りできる程度の道があれば駐車場として活用できます。
既存の建物が残っている場合、解体および最低限の整地が必要にはなるものの、一度形を整えてしまえば管理が楽になる点が特徴です。
駐車場として活用する場合、「月極駐車場」または「コインパーキング」のどちらかを選ぶのが一般的です。
どちらも不動産業者または専門業者に運用を委託するため、所有者側の負担が少なく済む点がメリットと言えるでしょう。
しかし、当然ながら、車やバイクを停める人がいなければ運営は成り立ちません。
再建築不可物件の近隣に駅や商業施設、会社があるなど、駐車場の需要が見込まれる場合に選択することをおすすめします。
昨今では「レンタル農園」と呼ばれる、農地の貸し出しサービスの人気が高まっています。
レンタル農園は、家庭菜園を持つスペースがない人や、一時的に野菜や花を栽培したい人、そのほか体験学習の実施場所としてなど幅広い需要があります。
安定した収益が期待できることから、再建築不可物件を畑にするのも一つの方法です。
ただし、農地に転用する場合は農業委員会や自治体への申請・手続きが必要なほか、宅地への再転用が難しい点に注意が必要です。
また、農地として機能を果たすよう定期的な手入れや管理が欠かせない点もデメリットと言えるでしょう。
一方で、都市部に集中しやすい駐車場と違い、畑は地方でもニーズがあるため、比較的場所を選ばない点がメリットです。
所有する再建築不可物件が狭く、車両の通行などが難しい場合は、自動販売機を設置する方法もあります。
専門業者に管理・運用を委託すれば、機材の導入費用やドリンク補充の手間もかかりません。
その分業者に手数料を支払う必要はありますが、複雑な手続きをせず土地活用をしたい方にはおすすめの方法と言えます。
また、規模が小さいため、駐車場の一角に設置するなど、他の活用方法とあわせて収益を見込める点もメリットです。
学校周辺や郊外の住宅地など、人の往来が多いエリアにおいて特におすすめの活用方法と言えます。
再建築不可物件は、トランクルームとしても有効に活用できます。
「トランクルーム」とは、敷地内に設置したコンテナを物置として貸し出す、いわゆる「貸倉庫サービス」の一種です。
トランクルーム市場は15年連続で拡大しており、2024年6月時点で1万3691店舗に達しています。
国内におけるファミリーレストランの店舗数が約1万店であることを考えると、非常に高いニーズがあることがうかがえるでしょう。
都市部においては特に物件の狭小化が進んでおり、自身の住まいだけでは家財を管理できないケースも少なくありません。
トランクルームは、そのような現代ならではの悩みに応える画期的なサービスと言えます。
コンテナハウスと異なり、屋内に人が滞在することを想定していないため、管理の手間がかからずトラブルが起きにくい点もメリットです。
駐車場や自動販売機と同様、専門会社への委託もできるため、初心者の方にもおすすめの活用方法と言えます。
再建築不可物件の活用方法が決まっていない場合、「とりあえず更地にする」のはあまりおすすめできません。
おすすめできない理由は以下の3つです。
所有する再建築不可物件を今後どのように活用するか、綿密に計画を立てたうえで決断しましょう。
再建築不可物件においては、既存の建物を解体した後の新築が認められていません。
そのため、更地にしてしまうことで土地活用の幅が制限されてしまうおそれがあります。
逆に、既存の建物であれば、大幅な改築などでない限りリフォームや修繕は可能です。
したがって、今ある建物をそのまま活かすことも選択肢の一つとして持てるのです。
所有する不動産に対して発生する固定資産税には、その土地が住宅用地である場合、最大1/6まで課税が軽減される特例措置が設けられています。
したがって、既存の家を解体して更地にしてしまうと、住宅用地の要件から外れてしまうため、固定資産税が最大6倍に跳ね上がるのです。
建物にかかる固定資産税がなくなっても、土地に対する課税額が上がることで、トータルで見ると大きな損失になりかねない点に注意しましょう。
再建築不可物件にある家を解体してしまうと、その土地には新たに家を建てられなくなります。
したがって、土地の価値そのものが大幅に下がり、売却しにくくなる点に注意が必要です。
土地を購入する人は、そこに家を建てたいと考えている人がほとんどです。
したがって、新築できない土地はまず購入候補から外れると考えたほうがよいでしょう。
再建築不可物件の売却を検討している場合は、更地にしないことをおすすめします。
再建築不可物件は、既存建物の有無にかかわらず、一般的な不動産会社では売却が難しいことがほとんどです。
不動産活用の予定がなく、早く家や土地を手放したいといった場合は、専門の買取業者に売却するのがおすすめです。
不動産の「買取」は、通常の仲介による売却と異なり、不動産活用のプロである不動産会社が買主です。
そのため、個人顧客からの需要が低く、なかなか売れない物件でも迅速な売却が期待できます。
「訳あり不動産相談所」では、再建築不可物件をはじめとした、多様な”訳あり”物件を専門に買取を行っています。
再建築不可物件の活用にお困りであれば、「訳あり不動産相談所」へ一度ご相談ください。
最後に、再建築不可物件やコンテナハウスに関するよくある質問にお答えします。
2025年4月の建築基準法改正で、「建築確認申請」の特例が縮小されることから、再建築不可物件でのリフォームが難しくなる可能性があります。
建築確認申請とは、建物の新築や増改築、リフォームなどにおいて、建築基準法に則した設計であることを証明するために必要な手続きのことです。
従来の建築確認申請には「4号特例」と呼ばれる特例措置があり、一定の面積以下の建物であれば申請不要で着工が可能でした。
しかし、2025年にこの4号特例が廃止、要件が見直されることで、建築確認申請が必要な建物の範囲が実質拡大します。
したがって、これまで再建築不可物件でも行えていたリフォームなどの改修工事が今後施工できなくなる可能性があると言えるでしょう。
コンテナハウスの床面積が10㎡(6畳)以下であれば、基本的に建築確認申請は必要ありません。
ただし、コンテナハウスの基礎が地面に固定されていないことと、防火地域・準防火地域以外に設置されることが条件です。
コンテナハウスと一口に言っても、物置を改良した簡易的なものから、本格的な居住に適したものまで様々な種類があります。
居住を想定して設計されたコンテナハウスは基本的に「建築物」として建築確認申請が必須となるケースが多いため、注意しましょう。
また、地域や自治体によっては10㎡以下でも申請が必要な場合があります。
コンテナハウスの設置を考えている場合は、事前に所属自治体に確認するのがおすすめです。
建築基準法に違反するかは、そのコンテナハウスが「建築物」として認められているかによって異なります。
床面積10㎡以上、または地面に基礎が固定されているコンテナハウスは原則として「建築物」扱いになるため、建築基準法に則した設計が求められます。
したがって、法基準を満たしていない場合は違反建築物として使用禁止にされたり、撤去されたりする可能性があるのです。
コンテナハウスそのものが違法というよりも、規模や立地、使われ方によっては建築基準法に違反することがあると考えるとよいでしょう。
建築基準法で定められた規定を満たすコンテナハウスは、建築物件に該当します。
建築基準法第2条を基に説明すると、「土地に定着し、屋根や壁を有するもの」である場合、建築物としてみなされます。
したがって、随時かつ任意に移設できないコンテナハウスの場合は、建築物に該当すると言えるでしょう。
建物の規模や建築確認申請の有無に関わらず、原則としてコンテナハウスには固定資産税が発生します。
なぜかというと、固定資産税は建築基準法ではなく、地方税法で定められたルールだからです。
コンテナハウスの活用手段を大きく左右する要素「土地への定着性」は、建築基準法と地方税法とでは解釈が異なります。
建築基準法が物理的な固定性を重視する傾向にあるのに対し、地方税法は使用期間や利用実態を重視します。
したがって、随時移設可能なコンテナハウスであっても、その土地への設置期間が長く、利用頻度が高い場合は固定資産税が課されるのです。
再建築不可物件は、建て直しができないため活用の幅が狭くなります。
コンテナハウスの設置のように建て直しせずに活用するか、再建築できるように工夫して活用するかの選択肢がありますが、いずれにせよ手間は費用がかかります。
活用の手間やコストをかけたくない、活用の予定がないといったケースでは売却して手放すことを検討するとよいでしょう。
とはいえ、売却するにしても活用しにくいことから仲介での売却がしにくいため、訳あり物件専門の業者での買取を視野に入れることをおすすめします。
訳あり不動産相談所では、再建築不可物件を含め仲介で取り扱ってくれない物件など処分に困る不動産の買取を行っています。
「物件の処分に困っている」
「他社では相手にされなかった」
「とにかく早く手放したい」
再建築不可物件を含め、取り扱いの難しい土地の売却でお悩みの際は、訳あり不動産相談所にご相談ください。
この記事の担当者

担当者③