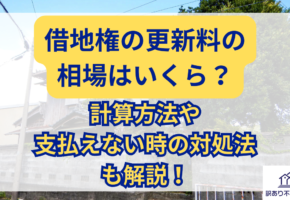
借地権の更新料の相場はいくらくらい? 計算方法や支払えない時の対処法も解説!
詳しく見る
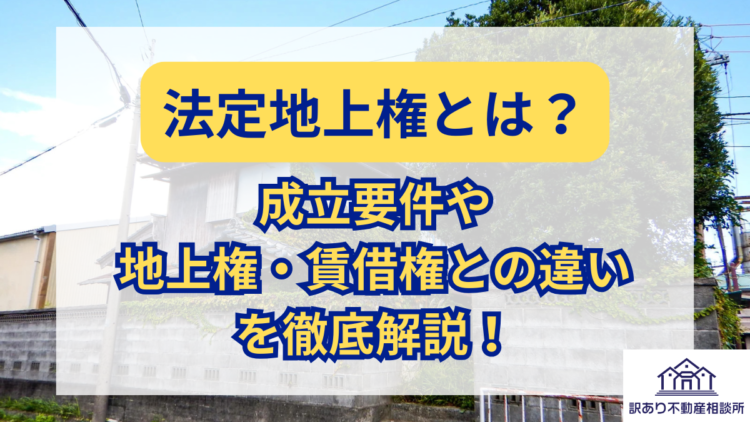
「法定地上権」は、不動産取引を行うなら特に知っておきたい不動産に関する権利の一つです。
しかし、具体的な内容や、どのような時に発生する権利なのか、実のところよくわからないという方も多いのではないでしょうか。
この記事では、法定地上権の概要や成立するケース・法定地上権と混同されやすい権利との違いまで詳しく解説します。
法定地上権のついた土地でお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
目次
法定地上権とは、「土地と建物の所有者が異なる場合に、建物の所有者が土地を利用する権利」のことを指します。
土地と建物の所有者が異なる場合に、土地の所有者の権利のみを認めてしまうと、建物を解体しなくてはならないといったケースも出てきてしまうでしょう。
まだ利用できるのにも関わらず、権利関係が要因で建物を解体しなければならないとなると、社会公益上損失が大きいため、建物の所有者の権利を保護する目的があります。
とはいえ、土地と建物の所有者が違う状況をあまりイメージできないという方もいらっしゃるかもしれません。
土地と建物の所有者が異なる代表的なケースが抵当権です。
物件購入時に、住宅ローンやアパートローンを組むと、土地や建物に対して抵当権が設定されます。
抵当権が設定されていると、万が一住宅ローンやアパートローンの返済が滞ったときに、土地や建物を売却して返済することになります。
中には土地の上に建物が建っているのにも関わらず、土地のみに抵当権が設定されていることがあります。
上記のようなケースで競売がなされると、土地の所有者が金融機関となり、土地と建物の所有者が異なることがあるのです。
土地と建物の所有者が異なると、建物の所有者は土地を使用できず、不法占拠としていつ立ち退きを請求されるか分からない状況になってしまいます。
このような事態から建物の所有者を守るために、建物所有者が土地を利用できる権利として「法定地上権」が認められているのです。
法定地上権は、民法・第388条に基づき特定の状況下で自動的に有効となります。
ただし、法定地上権を認められれば自由に土地を使えるわけではなく、利用の制限や賃料の支払いが必要です。
賃料を支払う場合は30年間土地の使用が認められ、期間終了後は土地所有者の合意の上で更新もできます。
法定地上権と似たものに地上権がありますが、両者の違いは何なのでしょうか。
結論からいうと、法定地上権は法律で自動的に定められるものであるのに対し、地上権は土地所有者の合意が必要です。
地上権も法定地上権と同様に、土地と建物の所有者が異なる場合に、建物の所有者の権利が保護される権利ですが、事前に土地の所有者の許諾を得る必要があります。
代表的なケースとしては、土地を借りて、土地の上に建物を建てるケースが挙げられます。
地上権というとやや難しい印象を持つかもしれませんが、より耳なじみのある言葉でいうと、「借地権」の1つです。
地上権が設定されている場合、建物の所有者は、土地の所有者の許可なしに建物の売却や貸出、担保の設定が可能となります。
担保の設定とは、抵当権の設定のことで、このために、土地や建物のどちらかだけに抵当権が設定されているケースが起こりうるのです。
次に、法定地上権と賃借権の違いを見てみましょう。
賃借権とは、契約に基づき、土地や建物などを貸したり借りたりする権利のことです。
賃借権は地上権と同様に、借地権の一種で、地上権が「物権」であるのに対し賃借権は「債権」です。
まとめると、以下のようになります。
地上権は、事前の合意が必要とはいえ、一度設定されると、土地の所有者の合意がなくとも、建物の売却や担保設定ができる強い権利です。
一方、賃借権の場合、土地の所有者の許可なしに建物を売却したり建て替えしたりすることはできません。
地上権は権利が強いために、実際に設定されるケースはほとんどなく、一般的な土地の貸し借りでは賃借権が設定されることが多くなっています。
なお、賃借権と法定地上権の違いとして、賃借権は土地の所有者の合意が必要であるのに対し、法定地上権は自動的に設定されるという違いがあります。
| 土地の所有者の許諾 | 土地の所有者の合意なしに建物の売却や抵当権を設定する | |
|---|---|---|
| 法定地上権 | 不要 | できる |
| 地上権 | 必要 | できる |
| 賃借権 | 必要 | できない |
地上権や賃借権は土地所有者の許諾が必要になりますが、法定地上権は法の定めるところにより、条件を満たせば自動で設定される権利です。
具体的には、以下のようなケースで法定地上権が成立します。
それぞれ見ていきましょう。
抵当権が設定された土地や建物が競売にかかった場合、法定地上権が設定されます。
なお、この要件で法定地上権が成立するには、過去の判例から、以下のような条件が必要とされています。
上記の要件を満たしたうえで、例えば土地のみが競売にかかり、所有者が異なる結果になった場合は、法定地上権が成立するのです。
これは、建物が存在するのにも関わらず、土地の所有者が変わったことが原因で、立ち退き要求などされてしまう危険性から、建物の所有者を守るためです。
強制競売の場合も、抵当権を要因とした競売と同様に、土地と建物の所有者が異なる結果になった場合は、法定地上権が成立します。
強制競売とは、抵当権によらない競売のことです。
住宅ローンなど不動産を担保としないローンや借金であっても、返済できない状況になった場合、債権者(お金を貸した側)が家庭裁判所に申し立てることで強制競売が可能です。
税金の滞納による強制処分(公売)についても、基本的には、強制競売と同じものと考えてよいでしょう。
抵当権を要因とした競売のように、事前に抵当権などの設定がなくとも、強制処分の結果、土地と建物の所有者が異なる結果になった場合、法定地上権が成立します。
基本的な流れは競売や強制競売と同じと考えてよいですが、個人や民間企業・金融機関が債権者となる競売に対し、強制処分の場合は公売により市役所や税務署といった行政機関が債権者になるのが特徴です。
法定地上権は、成立する条件下になれば発生するわけではありません。
土地と建物に対しても成立の条件があり、以下の4つを満たさなければ成立しないのです。
それぞれ詳しく解説していきます。
1つ目の条件として、抵当権設定時に、土地の上に建物が建っている必要があります。
そのため、抵当権設定後に建物を建てた場合は、法定地上権は認められません。
法定地上権が認められない場合、土地の所有者が変わった際に建物の撤去を求められる可能性があるため注意が必要です。
なお、建物の「存在」とは建物の有無が基準となり、登記の有無は影響しません。
抵当権は土地に建物が建っていると、土地と建物の評価をもとに融資額が決定され、なおかつ抵当権者は建物の存在を認識しています。
つまり、将来法定地上権が発生する可能性を予測できるため、登記がなくても建物があれば法定地上権が成立する可能性があるのです。
2つ目の条件として、抵当権設定時の土地と建物の所有者が同じである必要があります。
抵当権設定時点ですでに土地と建物の所有者が異なっている場合、賃借権などすでに他の権利が設定されているので、改めて法定地上権を成立させる必要はないとなります。
なお、建物・土地が共同名義のケースは、共有の内容によって法定地上権の成立が異なってきます。
土地と建物の両方を共有している場合、共有者の人数にかかわらず法定地上権が成立し、すべての所有者に対して権利や義務が発生します。
ただし、抵当権が土地と建物のすべてに設定されていることが条件です。
一方、土地と建物の両方をAとBの2名で共有しており、Aが所有する土地部分にのみ抵当権が設定されている場合は複雑になります。
抵当権に基づいて競売にかけられるのは、Aが所有する土地のみです。
この場合、落札者とBで土地を共有し、AとBで建物を共有するような状況になります。
この状態で法定地上権が認められると、抵当権に一切関与しないBが不利益を被ってしまうため、このケースでは法定地上権が成立しないとされています。(参考:https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/504/052504_hanrei.pdf)
共有名義の法定地上権は複雑になりがちなため、専門家に相談することをおすすめします。
3つ目の条件として、法定地上権は、競売によって土地と建物の所有者が分かれるケースで発生するのが一般的です。
つまり、そもそも抵当権が設定されていることが前提といえます。
ただし、前述のように抵当権の設定のない不動産であっても、強制競売・公売で所有者がわかれることでも法定地上権は認められます。
抵当権の設定は前提ではあるものの、必須ではない点は覚えておきましょう。
4つ目の条件として、法定地上権は土地と建物の所有者が分かれた場合に認められる権利です。
仮に、競売であっても落札後の土地と建物の所有者が同一であれば、所有者に不利益はありません。
つまり、土地と建物の所有者が同一のケースでは法定地上権は必要ないのです。
法定地上権は成立要件が細かいので、成立しないパターンについても理解しておくことが大切です。
成立しない代表的なパターンとして以下の2つが挙げられます。
法定地上権が認められるには抵当権の設定時に建物が建っている必要があります。
土地の抵当権設定後に建物が建てられるケースでは認められません。
この場合で、抵当権により土地の所有者が変わってしまうと、土地の所有者から建物の取り壊しを請求される恐れがあります。
しかし、それでは建物所有者の損失が大きくなるため、このケースでは土地と建物セットで競売する「一括競売」が認められています。
これによって、落札者は土地と建物両方の所有権を得られるため、法定地上権も必要ありません。
なお、一括競売では債権者が競売で回収できるのは抵当権を設定している方の売却代金のみです。
例えば、土地のみ抵当権を設定し一括競売したとしても、建物の代金からは借金の回収はできません。
抵当権設定時にあった建物を建て替えた場合、原則として法定地上権は認められません。
しかし、土地の抵当権設定者が土地と同順位の抵当権を建て替え後の建物にも与えた場合など、例外的に法定地上権が認められるケースがあります。
とはいえ、建て替えで法定地上権が認められるかはケースバイケースになるため、判断が難しいところです。
基本的には、抵当権後の再建では法定地上権は成立しないと考えておきつつ、専門家に相談するとよいでしょう。
法定地上権は以下のような期限が設けられています。
法定地上権の存続期間は原則30年と定められており、その後も特別な事由が無ければ20年後に更新、それ以降は10年ごとに更新されます。
反対に、特別な事由が発生すれば明け渡し請求が可能です。
更新を拒絶できる代表的な特別な事例は、以下の5つです。
法定地上権では、建物の所有者は土地の所有者に対して地代(賃料)を支払うことで、土地を利用することを認めています。
そのため、地代の支払いが長期間滞ると契約不履行とみなされ、土地の所有者は建物の所有者に対し、土地の明け渡しや建物の撤去を求められます。
ただし、1・2ヵ月程度の滞納で明け渡しを請求するのは難しく、3ヵ月以上など長期間の滞納が必要となってくるでしょう。
土地所有者と建物所有者の双方で合意が得られた場合、30年の存続期間中でも法定地上権を解除できます。
法定地上権をなくすための条件には規定が無く、当事者間で取り決めることが可能です。
とはいえ、法定地上権が無条件に解除されると建物所有者は家を手放さなくてはならず損失が大きくなります。
そのため、「土地所有者側で建物を買い取る」「建物の撤去費用を一部土地所有者が負担する」といった建物所有者側の負担を軽減するような条件も設けられるのが一般的です。
法定地上権は30年の存続期間の満了後、特別な事由が無い限り半永久的に更新されます。
しかし、以下のようなケースに当てはまる場合は更新を断り、法定地上権を無効化できる可能性があります。
なお、上記はあくまで一例です。
条件を満たしても必ず更新を断れるとは限らない点に注意しましょう。
建物の損傷や老朽化が激しく倒壊などの危険性があると認められれば、法定地上権を失効できることがあります。
このような場合、30年の存続期間の途中でも明け渡しを求めることが可能です。
また、地震や火事などの災害で建物がなくなった場合も同様に法定地上権は失効します。
土地所有者に建物を利用したい理由がある場合、明け渡しを請求することが可能です。
例えば、事業用地としての利用や自身の家を建てるなどで、すでにある建物を撤去したいと考えるケースもあるでしょう。
ただし、土地所有者の自己都合での明け渡し請求では、十分な立退料の支払いと建物所有者の合意が必要です。
「土地利用における正当な理由があり、かつ建物所有者に対し十分な退去費用を補償し、建物所有者の合意を得た」と認められた時のみ法定地上権を無効化できる可能性があります。
なお、たとえ相場以上の退去費用を支払えるとしても、建物所有者の転居が困難な場合は立ち退き請求が受理されません。
建物所有者の健康上の問題や仕事や家庭の都合で引っ越しができないといったケースでは、土地所有者からの補償額にかかわらず退去は却下され、法定地上権も残ることになります。
法定地上権が成立した後の地代(賃料)は、原則として土地所有者と建物所有者との話し合いによって決められます。
法律によって基準が定められているわけではないため、固定資産税・都市計画税の金額、公示価格・基準地価、相続税路線価などを基に算出するのが一般的です。
さらに双方の個人的な事情も加味した上で、お互いが納得する値段にしなければなりません。
明確な基準がなく話し合いで決まるため、地代の取り決めにあたってはトラブルが起きやすい点には注意が必要です。
話し合いによって合意が得られなかった場合は訴訟を起こし、裁判所に地代を決定してもらう必要があります。
しかし、裁判にまで発展すると、土地・建物双方の所有者に時間的、経済的な負担が発生します。
法定地上権のある土地は取扱いが難しく負担がかかるケースも少なくないため手放してしまうのも1つの手です。
訳あり不動産相談所では、法定地上権のついた土地のほか、さまざまな問題を抱えた物件を専門に買い取っています。
法定地上権が成立した土地の管理にお困りの際は、ぜひ訳あり不動産相談所にご相談ください。
最後に、法定地上権に関するよくある質問をみていきましょう。
法定地上権では、建物の所有者は土地を使用するための地代(賃料)を支払わなければなりません。
したがって、地代の支払いが滞れば契約不履行となり、法定地上権の無効化を申し立てられる恐れがあります。
ただし、法定地上権の無効化ににあたっては裁判所を通じての手続きが必要です。
地代が1〜2ヶ月未納であるからといって、すぐに退去を求められるわけではありません。
法定地上権は、抵当権設定時にすでに建っている建物で成立するため、抵当権を設定後に新しく建てた建物では認められません。
抵当権設定後に新築しさらにその土地の所有権が競売で他人に移った場合、建物の所有者は建物を使うために別途契約を結ぶ必要があります。
土地を借りて建物を建てた場合は、法定地上権ではなく賃借権が発生します。
賃借権の主な特徴は、以下の通りです。
このように、法定地上権と賃借権は全くの別物であるため、注意しましょう。
強制競売の結果、土地と建物の所有者が分かれれば法定地上権が認められる可能性があります。
法定地上権は土地と建物の所有者が異なる場合に、建物の所有者を守るための権利です。
基本的には抵当権が設定されていることが前提となりますが、抵当権が設定されない不動産で強制競売や公売により所有者が分かれたケースでも認められています。
ここまで、「法定地上権」について、権利の概要から成立に必要な要件、混同されやすい他の権利との違いまで詳しくお伝えしました。
競売や強制競売・公売などによって、もともとの所有者と落札者とで土地と建物の所有権が分かれることがあります。
土地の所有者が変わった場合、土地所有者からの要望があれば建物の所有者はその土地から退去しなければならないのがルールですが、それが難しいケースも少なくありません。
そのような場合に建物の所有者を守るため土地の利用を認める権利が法定地上権です。
一方、土地の所有者側は、せっかく手に入れた土地も法定地上権があると自由に使えず、管理や取り扱いに困るというデメリットがあります。
あるいは、法定地上権が成立した後の地代の取り決めに頭を悩ませる場合もあるでしょう。
法定地上権のある土地は、取り扱いが難しいので手放してしまうのも1つの手段です。
訳あり不動産相談所では、法定地上権のある建物付きの土地でも、積極的に買取を行っています。
「物件の処分に困っている」
「他社では相手にされなかった」
「とにかく早く手放したい」
法定地上権を含め、取り扱いの難しい土地の売却でお悩みの際は、訳あり不動産相談所にご相談ください。
この記事の担当者

担当者③