43条但し書き道路とは? 物件の再建築や売却方法も解説!
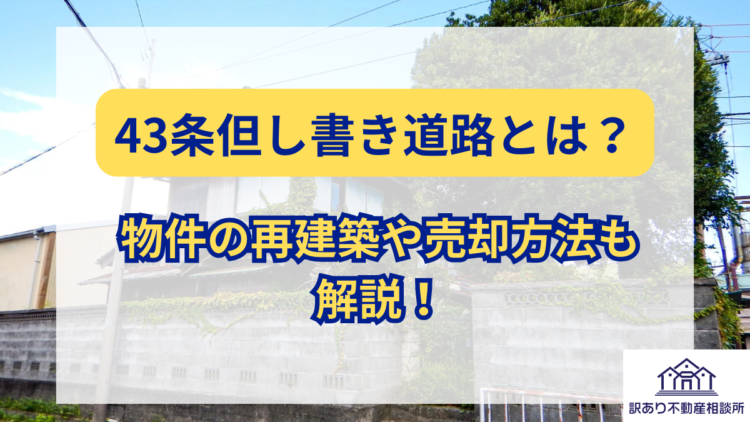
再建築不可物件は接道義務を果たしていないので、建て替えができない物件です。
特定行政庁の許可や建築審査会の同意により43条但し書き道路だと認められれば、再建築が可能になります。
本記事では、43条但し書き道路の許可申請手続きや、再建築および売却方法についてご紹介します。
目次
43条但し書き道路(43条2項2号許可)とは?
43条但し書き道路(43条2項2号許可)とは、建築基準法の接道義務を満たしていない「道」です。
敷地が幅員4m以上の道路に対して2m以上接している(接道義務)
敷地内の建物の軽微なリフォームは可能ですが、増改築や新たな建物を建てることはできません。
再建築不可物件の一種です。
43条但し書き道路(43条2項2号許可)は、建築基準法第43条2項1号または、建築基準法第43条2項2号の条件を満たすことで、再建築が可能となります。
| 建築基準法 | 再建築が可能となる条件 |
|---|---|
| 第43条2項1号 | ・幅員4m以上の道に2m以上接している敷地※道路に該当するものを除く※避難および通行の安全上に必要な国土交通省令に適合したもの ・利用者が少数であるもの ・その用途および規模に関する国土交通省令に適合したもの ・交通や安全、防火や衛生上の支障をきたさないと特定行政庁が認めたもの |
| 第43条2項2号 | ・敷地の周囲に広い空地を有する建築物 ・その他の国土交通省令に適合する建築物 ・交通や安全、防火や衛生上の支障をきたさない・建築審査会の同意を得て許可されたもの |
建築基準法第43条2項1号と2号の大きな違いは、建築審査会の同意および許可が必要な点です。
建築基準法第43条2項2号に該当する際には、建築審査会の同意や許可を得ることで、再建築が認められます。
建築基準法第43条2項1号の国土交通省令に適合する「道」の条件は次のとおりです。(建築基準法施行規則第10条の三)
農道その他これに類する公共の用に供する道であること(農道、河川管理道路、港湾施設道路など)
令第百四十四条の四第一項各号に掲げる基準に適合する道であること
※両端が他の道路と接続している
※延長が35m以下の袋路状道路(ふくろじじょうどうろ)
※終端および区間35mごとに自動車の転回広場が設けられている延長が35m超の袋路状道路
※自動車の転回に支障のない公園や広場などに終端が接続している袋路状道路
※幅員6m以上の袋路状道路
※特定行政庁が避難および通行の安全上支障がないと認めたもの
※砂利敷その他ぬかるみとならない構造であること
※縦断勾配が12%以下であり、階段状でないもの
※排水に必要な側溝や街渠その他の施設を設けている
詳しくは、物件の所在する市区町村役場にて確認することをおすすめします。
43条但し書き申請の対象となる条件
43条但し書き申請の対象となる条件として、以下の4つが挙げられます。
- 接道義務を満たしていない
- 幅員4m以上の道に2m以上接している
- 周囲に一定の空地がある
- その他の基準を満たしている
接道義務を満たしていない
建築基準法に定められた接道義務を満たしていない敷地は、43条但し書き申請の対象となり得ます。
敷地が幅員4m以上の道路に対して2m以上接している(接道義務)
この場合の道路は、建築基準法第42条「道路の定義」に該当するものです。
| 建築基準法 | 内容 |
|---|---|
| 第42条1項1号 | 道路法で定められた幅員4m以上の道路※国道、県道、市道、区道などの公道 |
| 第42条1項2号 | 都市計画法などで定められた幅員4m以上の道路 |
| 第42条1項3号 | 建築基準法の施行(1950年11月23日)前より現存する幅員4m以上の道路 |
| 第42条1項4号 | 道路法や都市計画法などで2年以内に施工予定の事業計画を有する特定行政庁が指定した幅員4m以上の道路 |
| 第42条1項5号 | 民間による建物の敷地目的での土地の申請後、特定行政庁より位置の指定を受けて新設された幅員4m以上の道路(位置指定道路) |
| 第42条2項(みなし道路) | 建築基準法の施行(1950年11月23日)前に建物が立ち並んでいた、幅員1.8m以上4m未満の特定行政庁より指定された道路 |
幅員4m以上の道に2m以上接している
幅員4m以上の道に2m以上敷地が接している物件も、43条但し書き申請の対象となる条件のひとつです。
道路ではなく、「道」と記載されている点に注意しましょう。
建築基準法施行規則第10条の三に該当するものが、法的な基準を満たす「道」と定義されています。
周囲に一定の空地がある
周囲に一定の空地がある物件も、43条但し書き申請の対象です。
空地の例として、公園や広場や緑地が挙げられます。
ただし、43条2項2号許可の案件となるため、建築審査会の同意や許可を得ることが必要不可欠です。
その他の基準を満たしている
その他の基準には、敷地の通路や建築物が該当します。(建築基準法施行規則第10条の三)
・避難および通行の安全上の目的を達成するための十分な幅員を有する通路
※建築物の用途や規模、位置や構造に応じたもの
・道路につながる通路に対して有効に接する建築物
43条但し書き申請の流れ
ここからは、43条但し書き申請の流れをご紹介します。
法的な手続きとなるため、難しいと判断された際には、専門家に依頼するのもひとつのやり方です。
- 特定行政庁との事前相談・協議
- 書類の作成・提出
- 建築審査会の審査
①特定行政庁との事前相談・協議
43条但し書き申請の最初の手続きは、特定行政庁にて、お住まいの物件が43条但し書き申請の対象であるかを確認することです。
特定行政庁は、建築基準法で定められた建築主事が配置された自治体です。
大まかには人口25万人以上の市が、特定行政庁と捉えておけば良いかもしれません。※地域によっては、都道府県庁が特定行政庁の場合もあります。
建築主事が所在する市町村役場の建築課や、建築指導課が窓口です。
お住まいの地域の特定行政庁は、全国建築審査会協議会の「特定行政庁一覧」を参照してください。
特定行政庁への事前相談の際には、次の書類を持参していくと、スムーズに進行するかと思われます。※神奈川県横浜市の場合です
- 案内図
- 周辺現況図
- 登記事項証明書(または登記簿謄本)
- 建築計画概要書
- 認定路線図
- 道路台帳平面図
- 区域線図
- 現場写真
必要書類は自治体ごとに異なるため、事前に自治体の公式サイトで確認しておきましょう。
②書類の作成・提出
特定行政庁との事前相談および協議の後、現地調査を経て、43条但し書き申請の対象であることが確認されたら、申請に必要な以下の書類を準備することになります。※神奈川県横浜市の場合です
- 許可申請書※43条2項1号認定の場合は認定申請書
- 委任状
- 公図
- 全部事項証明書(土地登記簿謄本)
- 誓約書
- 印鑑登録証明書
- 案内図
- 周辺現況図 など
必要書類は自治体ごとに異なります。
あらかじめ自治体のサイトで確認しておきましょう。
③建築審査会の審査
特定行政庁への書類の提出後は、建築審査会の審査に進む必要があります。※神奈川県横浜市を例にした手続きの流れです
- 建築基準法に定められた道路に対して2m以上接していない敷地
- 建築主事への事前相談(建築基準法第43条2項の規定)※神奈川県横浜市の建築主事は、市街地建築課許認可担当
- 認定基準または包括同意基準に該当していない物件
- 道路判定委員会の包括同意基準に該当しない物件
- 個別提案基準案件として、建築審査会に提案
- 提案者への回答 ※事前相談より提案者への回答は2週間から3週間後
- 道路判定委員会にて図面審査
- 図面審査より2週間から3週間後に建築審査会の同意を得る
- 消防同意を得てから許可通知書の交付(再建築の許可)
- 建築指導課または指定確認検査機関の建築確認申請に進む ※建築審査会の開催から1ヶ月から2ヶ月後
建築確認申請後に許可がおりた時点で、物件の再建築が可能となります。
包括同意基準の要件を満たすと手続きが簡単に!
43条但し書き申請の際、包括同意基準の要件を満たしていることで、建築審査会の審査を経なくとも、物件の再建築が認められます。
神奈川県横浜市の場合は、以下の手順です。
- 建築基準法に定められた道路に対して2m以上接していない敷地
- 建築主事への事前相談(建築基準法第43条2項の規定)※神奈川県横浜市の建築主事は、市街地建築課許認可担当
- 申請された物件が包括同意基準を満たしている
- 包括同意基準案件として、建築審査会への提案が不要となる
- 提案者への回答 ※事前相談より提案者への回答は2週間から3週間後
- 消防同意を得てから許可通知書の交付(再建築の許可)
- 建築指導課または指定確認検査機関の建築確認申請に進む ※提案者への回答より2週間程
建築審査会の審査が省かれる分、再建築の許可までの時間が大幅に短縮されます。
神奈川県横浜市の包括同意基準を、次の表にまとめてみました。
| 基準の種別 | 概要 |
|---|---|
| 建築審査会包括同意基準1 | 広場などに接する敷地に建てる建築物 |
| 建築審査会包括同意基準2 | 幅員4m以上の道(公的機関などが管理するもの)に接する敷地に建てる建築物 |
| 建築審査会包括同意基準3-2 | 以下の規定に基づく制限解除を受けた建築物 ※都市計画法第37条次の規定に基づく許可を受けた建築物 ※土地区画整理法第76条 |
| 建築審査会包括同意基準3-3 | 1999年5月1日時点で現存する路線型の道などに接する敷地に建てる建築物空地幅員:1.8m以上中心後退:2m以上 |
| 建築審査会包括同意基準3-3の2 | 1999年5月1日時点で現存する専用型の通路の終端などに接する敷地に建てる建築物空地幅員:1.5m以上延長:20m以下 |
| 建築審査会包括同意基準3-4 | 1999年5月1日時点で現存する路線型の道などに接する敷地に建てる建築物空地幅員:0.9m以上1.8m未満中心後退:2m以上 |
| 建築審査会包括同意基準3-4の2 | 1999年5月1日時点で現存する専用型の通路の終端などに接する敷地に建てる建築物空地幅員:0.9m以上延長:15m以下 |
| 建築審査会包括同意基準3-5 | 1999年5月1日時点で現存する路線型の道などに接する敷地に建てる建築物空地幅員:0.9m以上中心後退:1.35m以上2m未満 |
※他の自治体の包括同意基準については、自治体ごとの公式サイトで確認してください
43条但し書き道路のデメリット・トラブル
43条但し書き道路は、建築基準法の接道義務を満たしていない「道」のため、購入や売却、増改築や建て替えの際、申請手続きが必要不可欠です。
ここからは、43条但し書き道路に想定されるデメリットおよびトラブルをご紹介します。
- 基準を満たしても100%建て替えできるとは限らない
- 道の共有者全員が合意しないと申請が行えない可能性がある
- 住宅ローンの審査が下りにくい
- 高く売るのは難しい
基準を満たしても100%建て替えできるとは限らない
43条但し書き道路に接する敷地は、建築基準法43条2項2号の許可および、建築審査会の同意を条件として、建て替えや増改築が可能となる物件です。
ただし、物件の状態によっては、建築審査会の審査を通過できないことも想定されます。
特に、43条但し書き道路の物件を購入または売却する際には、建築審査会の同意の有無を確認してください。
買主や売主より、契約不適合責任を問われるかもしれません。
中には法律の改正によって、改正以前の基準は満たしていても、法改正後の基準から外れるケースも見受けられます。
くれぐれもご注意ください。
道の共有者全員が合意しないと申請が行えない可能性がある
43条但し書き道路の対象物件には、複数の共有者が存在する「道」も含まれます。
通路として使用されている道の場合、自治体によっては、共有者全員の同意を得ることが必要になります。
共有者との良好な関係を保つことも、将来の建て替えや増改築のための準備と言えます。
特に相続で代替わりした際には、きちんと挨拶をしておきましょう。
住宅ローンの審査が下りにくい
43条但し書き道路に接する敷地は再建築不可物件です。
住宅ローンの審査が難航するおそれがあります。
申請手続きから実際の再建築や売買までの時間を要することから、金融機関によっては、融資を見送られるかもしれません。
特定行政庁からの許可や、建築審査会の同意を得ていることを証明できるか否かがカギとなります。
高く売るのは難しい
43条但し書き道路の物件は、周辺相場と比べて価格が割安になる傾向があるのは否めません。
将来的に再建築不可物件となるリスクを有することがその理由です。
一般の売却の場合、買主が見つからないことも考えられます。
特に相続などで、早期の現金化を望む方は、専門業者への売却(買取)を検討してみてはいかがでしょうか。
訳あり不動産相談所は、43条但し書き道路を含む再建築不可物件の豊富な買取実績があります。
是非一度、ご相談ください。
43条但し書き道路に関するよくある質問
ここからは、43条但し書き道路に関するよくある質問にお答えします。
- 43条但し書き道路の改正内容は?
- みなし道路とは?
- 43条但し書き道路 セットバックとは?
43条但し書き道路の改正内容は?
2018年9月25日に施行された改正建築基準法では、43条但し書き道路に関する改正が行われました。
以下の条件を満たす敷地に関しては、特定行政庁の認可のみで、建築審査会の同意は不要です。
- 幅員4m以上の道に敷地が2m以上接している ※農道や林道、河川などの管理用の道など
- 延べ面積200㎡以内の戸建住宅 (参考:岡山市)
- 特定行政庁が交通上、安全上、防火上、衛生上支障をきたさないと認めたもの
みなし道路とは?
みなし道路とは、建築基準法第42条2項に該当する道路です。
建築基準法の施行(1950年11月23日)以前に、建物がすでに立ち並んでいた幅員1.8m以上4m未満の特定行政庁より指定された道路を指します。
みなし道路に接する敷地に戸建住宅などを建てることは可能です。
ただし、道路の中心線より2m下がった位置に、道路の境界線を設定することが求められます。(セットバック)
43条但し書き道路 セットバックとは?
セットバックとは、道路の幅を広げる目的で、所有している敷地を提供するものです。
道路の境界線を、道路の中心線より2m下げるための工事が求められます。
河川や線路などに面している道路の場合には、道路の反対側より4mの位置に道路の境界線を設定する形です。
セットバックした部分は敷地の所有権内ですが、建物や塀、門や花壇などを設置することは認められていません。
43条但し書き道路の場合、敷地の所有者がセットバックを施すことで、建築審査会の同意を得なくとも再建築可能物件に切り替わる可能性があります。 ※特定行政庁の許可は必要です
但し書き申請が必要な物件の売却は専門の買取業者へ!
ここまで、43条但し書き道路を再建築可能とするための申請について紹介してきました。
43条但し書き道路は、特定行政庁の許可や建築審査会の同意を得ることで、再建築可能となる物件です。
申請手続きから許認可までの時間がかかるだけでなく、必ずしも建て替えができるとは限りません。
43条但し書き道路などの再建築不可物件の処分を考えている方は、買取実績が豊富な専門業者への売却も検討しましょう。
この記事の担当者

担当者③

